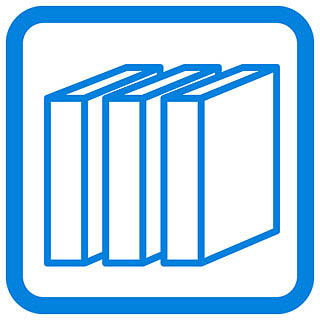「ヴァリス」
フィリップ・K・ディック/サンリオSF文庫/1982年 580円 |
 |
今はなきサンリオSF文庫の一品。新刊当時、朝日新聞の日曜版に出ていた書評と表紙の絵に惹かれて購入した。だが、442ページもある大著の上に中身は難解。巻末に用語解説まである小説なんて初めて遭遇した。
今となっては中身についてはほとんど記憶にない。むしろ印象に残っているのは、その不思議な表紙の絵である。作者は藤野一友という人で、のちに雑誌「美術手帳」でも取り上げられていたので買ってみた。そこで紹介されていたほかの絵も、この絵同様に不思議なものが多かった。
|
|
|
「謎のカスパール・ハウザー」
種村季弘/河出書房新社/1985年 1800円 |

ご購入はこちら
|
今年、話題となった「謎のピアノマン」。結局、身元が判明したらしいが、この話を聞いて「カスパール・ハウザー」を連想した人は、おそらくヨーロッパでは少なくなかったのではないだろうか。
カスパール・ハウザーは、1828年5月にドイツの町に突然現れた謎の少年。少年は「兵士になりたい」「馬」「わからない」という言葉しかしゃべれず、ロウソクの火をつまもうとし、時計を生き物と思っておびえ、男女の区別もつかなかったが、まるで動物のように嗅覚にすぐれ、暗闇でも目がきいたという。当時の犯罪学者は、「高貴な家柄の私生児として生まれ、人目をはばかって暗い地下室のようなところで育てられたのでは」という説を発表している。そのためナポレオン遺児説まで唱えられたそうだ。だが、カスパール・ハウザーが謎に満ちているのは、その最期である。1833年、正体不明の男に刺され、謎の言葉を残して生涯を閉じる。彼の墓標には「ここに現代の謎、眠れり。彼の生まれは不明で、彼の死は不可解なり」と刻まれているという。
本書は、この怪事件を追った長編伝記である。
|
|
|
「消された秘密戦研究所」
木下健蔵/信濃毎日新聞社/1994年 2800円 |

ご購入はこちら
|
陸軍登戸研究所といえば、第2次大戦中に生物・化学兵器のほか、風船爆弾や、はたまた電磁波兵器のようなものまで研究開発していた極秘の研究機関である。本書は登戸研究所の歴史に始まり、疎開先の信州での活動について克明に追っている。
ノモンハン事件の時に細菌兵器が使われた、というのは知らなかった。ただ、実際にはほとんど効果がなかったのだという。だが本書を読むと人体実験の生々しい証言など、歴史の闇に消えかけていた真実が見えてくる。
かねてより私は旧陸軍では、スパイ養成機関でもあった中野学校とともに、この登戸研究所については関心があった。その一級の資料といえそうだ。
|
|
|
「図説 北朝鮮強制収容所」
安明哲/双葉社/1997年 1400円 |

ご購入はこちら
|
脱北した元北朝鮮強制収容所警備隊員自らが目の当たりにした強制収容所における凄惨極まる所業の数々。これが血のかよった人間のすることなのだろうか。その実態は以前から多少は知っていたが、想像以上のものであった。
著者自らが描いたイラストは稚拙だが、実体験をもとにしているだけに非常にリアリティーがある。気の弱い人にはお勧めしない。だが、これが北朝鮮という国の本性である。このような恐ろしく非人道的なことをまさに「今」も続けている隣国が存在するということから目をそらしてはいけない。
|
|
|
「ハーメルンの笛吹き男−伝説とその世界−」
阿部謹也/平凡社/1974年 1800円 |
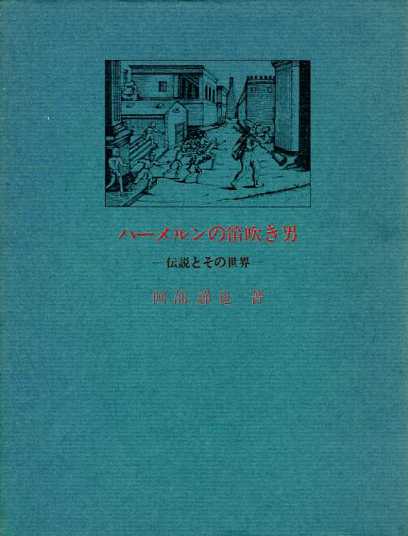
ご購入はこちら |
街中のネズミをすべて捕ればお金を払うとハーメルン市民はネズミ捕り男と取引する。そこで男が笛を吹き鳴らすと家々から一匹残らずネズミが出てきて男のまわりに群がった。男がネズミを誘導して街を出て川に入ると、ネズミはみな男のあとについて行って溺れ死んでしまった。だが、男が本当にネズミを駆除したのを見たハーメルンの人々は、いろいろな理由をつけて支払いを拒否する。怒った男は街を出て行くが、のちに戻ってきて、再び笛を吹く。すると今度はネズミではなく子供たちが集まってきた。130人もの子供たちは男について街を出たが、山に着くと男もろとも姿を消してしまう。これが「ハーメルンの笛吹き男」伝説の概略である。
だが、少なくともハーメルンの子供たち130人が近郊にあるカルワリオ山で行方不明になったのは、史実だったというのである。その日付もはっきりわかっていて1284年6月26日なのだそうだ。著者は、それが歴史的事実であることを発見し、さらにこの伝説に隠された真実を追っていく。
|
|
|
「南京事件 証拠写真を検証する」
東中野修道ほか/草思社/2005年 1500円 |

ご購入はこちら
|
アメリカでベストセラーになった「レイプ・オブ・南京」などで南京大虐殺の証拠として掲載された写真を丹念に調べ、結局「証拠写真として通用する写真は一枚もなかった」という結論を導き出している。本書を読むと「レイプ・オブ・南京」はもちろんだが、中国政府が、いかに世界や国内の反日意識を高めるべく、嘘八百を並べているのかよくわかる。
私はあくまで中立的立場で読み始めたが、一部に同意できない部分もなくはなかったものの本書が指摘する内容に無理な点はまったく感じなかった。論理的に納得できる主張になっている。著者は最後に「私たちは虐殺があったかなかったかを検証しようとしたのではない。あくまで南京大虐殺の証拠に使われている写真が果たして証拠写真として通用するかどうか検証したのだ」とも語っている。それは「真実」を追求する姿勢として好感が持てる。
南京大虐殺については、また折をみて本サイトでも詳しく書こうと思うが、さまざまな意見を聞くこともせずに無思考的に中国のいうことをそのまま受け入れるようなことはしない方がいい。まずは本書を読んでみられることをお勧めしたい。すると中国という国の真の姿が、少しは見えてくるだろう。
|
|
|
「綺想科学論」
南山 宏/学習研究社/2005年 1900円 |

ご購入はこちら
|
人によっては、いわゆる「トンデモ本」のひとつということになるのかもしれない。確かににわかには信じがたい仮説が目白押し。特に頭がガチガチに固くなってしまった人には、受け入れがたいだろう。確かに私から見ても「これはちょっと違う」と感じたものもなくはなかった。例えば「土星の輪は異星人の建造物だった」の証拠として掲載されているP177、179の写真である。これは単に惑星探査機による写真データを電送する折のエラーのようなものではないのだろうか。写真のフレームとは無関係というが、P181で示されている写真で「超巨大物体」なるものが、写真のフレームと完全に並行になっているのが何より気になる。
ただ、ほかの仮説には興味深いものもあったし、著者が最後に書いている「私的コラム・心霊現象は科学的に完全否定できるか」は、非常に共感を覚えた。
著者は、次のように書いている。「(ある科学者は)霊媒の降霊実験や心霊写真などは(略)すべて詐術やトリックで説明できるとして過去の実例を列挙している。部分を否定することによって同種の現象全体を否定してしまうわけだ。だが、否定論者は、論理学上の基本手続きをひとつ、さりげなく省略しているのだ。部分を取り上げて全体を否定するには、その前に全体のどの部分をとっても同質であることを証明しなければならない。未解明の現象である以上それは不可能だから、素知らぬふりでその手続きを飛ばしてしまう」。
まったくその通りである。科学者の中には、論理のプロである割に、このような「ごまかし」をする人がいる。もちろん、多くの一般の人は、科学者がうまくごまかしたことに気づきもせずに、その説明に「なるほど」と納得してしまう。私はこのような物の考え方は、科学の手法として間違っていると思う。可能性が低いから「排除」するのではなく、否定できる根拠がなければ「保留」しておくべきなのだ。論理を組み立てる際に、最も可能性の高い方を選択することを繰り返すことで、真実から大きく方向がずれてしまうということもある。日本人にノーベル賞受賞者が少ないのも、ひょっとするとこの辺に理由があるのかもしれない。ノーベル賞を多く受賞している欧米の科学者の方がはるかに考え方に幅があり、安易に可能性を「排除」しない。これは犯罪捜査でも同じことである。目撃証言にこだわりすぎて別の可能性について安易に「排除」してしまうことが、昨今の検挙率低下を招いているのではないか。最もありがちな説に飛びつくのではなく、否定する根拠がなければ、とりあえず可能性が低い説も「保留」しておくべきなのだ。それは科学だけでなく、世の中のあらゆる面でいえることだと思う。
|
|
|
「プリオン説はほんとうか?」
福岡伸一/講談社ブルーバックス/2005年 900円 |

ご購入はこちら |
狂牛病の病原体として、一般にもすっかり知られるようになった異常型プリオンタンパク質。だが、プリオン説を支持する証拠がある一方で、いろいろな弱点があるのも事実だという。そのため異常型プリオンタンパク質が検出されないからといって、その臓器や組織の部位が安全であり、それを食用にしても問題ないという考え方は論理的ではない、と著者は主張する。
実は病原体がウィルスであることを疑わせる実験結果も存在し、それも踏まえて、著者は、正常型プリオンタンパク質が病原体感染のレセプターとして機能しており、ウィルス感染の副産物として異常型プリオンタンパク質が脳に蓄積されているとする。
もはや、狂牛病や人のクロイツフェルト・ヤコブ病が異常型プリオンタンパク質によるものという前提で、米国産牛肉輸入再開においても論が進んだような感もあるが、著者がいうようにそうではないのかもしれない。
また古くから知られていた羊のスクレイピー病に始まり、プリオン説が出てくるまでの研究の経緯も、おもしろかった。
ちなみに著者は分子生物学が専門の青山学院大学理工学部教授。
|
|
|
「太陽系シミュレーター」
社団法人日本天文学会監修・Solar System Simulator Project編/
講談社ブルーバックス/2003年 1900円 |

ご購入はこちら |
前項に引き続き、ブルーバックスをもう一冊紹介。本というよりも付録のソフトがお勧めの一品。帯にあるコピー「太陽系宇宙を思いのままに操作!」の言葉に嘘はない。設定でパソコンへの負荷度を高くすると、実にリアルな宇宙空間が再現され、太陽系をぐるっと回したり、冥王星に着陸してみたり、まさに太陽系内の宇宙旅行を存分に体験できるというわけだ。
私のパソコンにはハードディスクにすべてのファイルを丸々インストールしてあり、原稿書きで作業に詰まると気分転換に火星や天王星目指して宇宙旅行に出かける。いくらパソコン上の仮想空間とはいえ、いやはや、これはなかなか楽しい。これで1900円は安い!
|
|
|
「心理学パッケージ 不思議な世界・心の世界」
小川捷之ほか/ブレーン出版/1985年 1800円 |
 |
大学生の時、心理学に興味を覚え、心理学の本を何冊も読んだ。中でもおもしろかったのがこの本。シリーズものでPart5まで刊行されていたが、今も販売されているかどうかは知らない。数ページ単位で、さまざまな心に関する話題が読み切りで紹介されているので、素人にもとっつきやすい。
例えば人間は興味をもつ対象を見るとき、そうでないときよりも瞳孔が広がる…など。だが、私が一番興味深く読んだのは「クレーパー・ハンス」の話だった。ハンスというのは、20世紀初頭に世界的に有名になった馬の名前。ハンスは非常に頭のいい馬で、人間の質問、例えば四則計算も足で床を叩いて正しく答えたという。しかも飼い主はこの馬で金儲けしようともせず、自分が不在の時にも快く馬を貸したという。つまり「いかさま師」という要素はまったくなく、調査した学者も「いかなるトリックもなかった」と報告している。
だが、その後、ハンスのからくりが判明した。ある学者がハンス以外にはその場に居合わせた誰も答えを知らない質問をした。するとハンスはいつまでも足を打ち続けやめようとしなかった。そのことからハンスは何も考えてはおらず、床を打つのをやめよという人間の合図を持っていたことがわかったのである。つまり正しい答えの回数だけ足を打ったところで、まわりにいる人間には無意識のうちにごく微細な緊張のほぐれが生じる。それをハンスが読んで足を打つのをやめていたというのである。ハンスは人間の質問を理解し、それを考えて答えていたわけではなかったが、別の意味で驚異的な能力が判明したのである。そんな心にまつわる話がいろいろ載っており、おもしろかった。
|
|
|
「ヴォイニッチ写本の謎」
ゲリー・ケネディほか/松田和也・訳/青土社/2006年 2800円 |

ご購入はこちら
|
「ヴォイニッチ写本」というのは、1912年に書籍商のウィルフドルフ・ヴォイニッチによって南ヨーロッパの古城で発見され、現在はアメリカ・イェール大学が所蔵する謎の写本。そこに書かれている文字や言語はまったく未知のものだが、しかしでたらめに書かれているわけではなく、何らかの語彙と文法に従って書かれていることが最新の研究でわかっているという。また地球上に存在しない植物や曼陀羅のようにも見える天体図らしき彩色図なども多数収録されているが、誰がいつ何のために書いたものか何ひとつわかっていない「世界最大の謎の写本」というのである。本書にはカラー図版は少ないが、その限られた図版を見るだけでも、ますます謎が深まるばかり。
表紙にも掲載されているヒマワリにも似た植物は、植物学的に見れば、明らかに「頭花」の形態をしているのがわかる。だが、その葉にはヒマワリに似ても似つかない切れ込みがあり、さらに不思議なのは根っこにはイモ状の塊根のようなものまで描かれているのだ。これはいったい何だ?
|
|
|
「ツチノコ」
木乃倉茂/碧天舎/2004年 1000円 |

ご購入はこちら
|
ツチノコといえば、西日本を中心に目撃者が多いにも関わらず、これまで存在を証明するものが何ひとつなかった未知の動物。本書は、そのツチノコ(本の中では「野槌」と呼ばれている)を捕らえて飼育していたという衝撃的な内容。
昭和17年、軍令部による長野県埴科郡西条村の工事現場で掘り出された土の中から、それは姿を現したという。のちに化学の研究員であった著者の祖父が飼育することになり、詳細な観察記録や写真に残した。その記録を基に書かれたのが本書で、これまでの目撃談とは一線を画した内容になっている。
詳細なスケッチ、写真、生態観察に留まらず、採毒もされて毒の化学組成まで調べられているのだ。当然モノクロながらも鮮明な生態写真には、びっくりした。1年後、ツチノコは死んでしまったので解剖され骨格標本にされたが、その標本は東京大空襲で失われたという。せめて骨格標本があれば、ツチノコの存在を科学的に証明することができたのだが。あるいは爬虫類の専門家によって論文が書かれていれば…。いづれにしても極めて残念だ。
過去にそんな事実があったというのがわかったものの、結局、存在を裏付けるものがないのでツチノコの存在は発展しそうでこれ以上発展しないのだが、本書の内容は想像以上だった。
ちなみに二十数年前に亡くなった私の母方の祖母は、若かりしころツチノコらしき短胴の奇妙な形のヘビを目撃したことがあると生前、話していた。それが本当に未知の生物だったのかどうかはわからないが、ツチノコの目撃者が多いのは事実である。もちろん、その中には小動物を飲み込んで膨れたヘビを誤認した例もあるかもしれないが、すべてそうだったとも断定できない。いつかツチノコが再発見され新種のヘビとして発表される日がくるのを願うばかりだ。
|
|
|
「Newton別冊 時間の謎」
ニュートンプレス/2001年 2142円 |

ご購入はこちら
|
科学のテーマ毎にきれいなイラストや写真を多用し、一般向けに比較的わかりやすく解説されたニュートン別冊シリーズの1冊。
この「時間の謎」では、最新の研究をもとに時間とは?、空間とは?、あるいは宇宙とは何か、について教えてくれる。ひと昔前なら、哲学の範疇とされ誰も答えられなかったであろう「時間はいつから始まったのか」とか、「宇宙の誕生よりも前はどうなっていたのか」とか、「宇宙の果てのさらにその先には何があるのか」といった質問にも、ある程度の答えが用意され、私たちの日常から遥かに超越した難しい題材を無難にまとめている。だが高校の時、物理が不得意だった私には物理学用語オンパレードの記事全部を読むのは正直しんどい。しかし、そんな究極の質問に対する答えを知るのは快感だった。科学はここまで到達しているのだ。すごいと思うと同時に、私たちが五感で感じることのできる世界のなんとちっぽけなことか。そんなことも感じた。
|
|
|
「深海生物ファイル」
北村雄一/ネコ・パブリッシング/2005年 1619円 |

ご購入はこちら
|
深海に棲息する奇天烈な容姿をしたさまざまな生物をカラー写真で紹介し、その個性的な生態についても解説されている。昔から身近な生物ですら、私は「不思議」に感じることが多かったのだが、深海生物となると、その不思議さたるや、もうお手上げ。進化の結果、これほどの多様性が生まれたのだ、といくら説明されても彼らの奇天烈な容姿をいったい誰がデザインしたのだ、という疑問を払拭するのに苦労する。
それにしても実に異様な形態、生態を見せる深海の生物たち。中でも新種の大型イカの話には惹きつけられた。2000年ころから深海に奇妙なイカがいると研究者の間で知られるようになり、2001年に正式に報告されたばかりでまだ名前もないという。そのイカは水深2000〜4000mに棲み、腕を含めると3〜7メートルにもなる大型のイカなのだが、腕が胴体から直角に出て、途中から先は垂れる独特の姿をしているのである。
この本にも紹介されているタコに近い生物というコウモリダコは、以前NHKの番組で海中を泳ぐ鮮明な映像を見たが、こいつも見た瞬間「参った!」と思わずにいられなかった。宇宙から見ればちっぽけな地球という惑星に、これほどの生物多様性があることに改めて驚かされる。
|
|
|
「生物と無生物のあいだ」
福岡伸一/講談社現代新書/2007年 777円 |
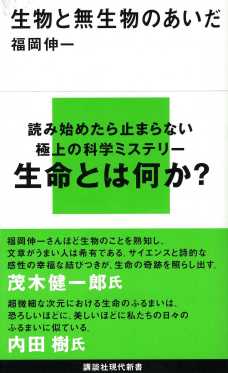
ご購入はこちら
|
以前、このページでも紹介した『プリオン説はほんとうか?』の著者の最新刊。話題になっているようだったので、早速読んでみた。普通、この手の本は読者を引き込むほどの中身を備えていることは少ない。だが、本書は違う。ヘタな作家よりも、よほど巧みな文章であり、「読み始めたら止まらない」という帯の言葉はその通りだった。
人は瞬時に生物と無生物を見分けるが、それは生物の何を見ているのか。著者は、生物のように自己複製能力があるのに結晶化させることもできるウィルスを挙げ、生物と無生物のあいだをたゆたう何ものかであり、生物であるとは定義しないという。では生物とは何なのか。DNAが二重らせん構造をしていることを発見したワトソンとクリックの話に始まり、読者をどんどん生命の本質に導いていく。
生命とは機械的生命観が描く分子機械ではないのだ。本書を読めば意外な生命の姿が見えてくる。また、わかりやすく解説されたPCR(ポリメラーゼ連鎖反応)のしくみも今回初めて詳しく知り、その素晴らしいアイデアに感心しきりであった。難解な部分もあるが、一気に読んでしまった。
|
|
|
「韓国が世界に誇る ノ・ムヒョン大統領の狂乱発言録」
坂 眞/飛鳥新社/2007年 1200円 |

ご購入はこちら
|
「盧武鉉(ノ・ムヒョン)大統領は頭がどうかしている」。これは私の感想ではない。前の前の韓国大統領・金泳三(キム・ヨンサム)の発言なのだそうだ。だが、ノ・ムヒョン大統領が普通の常識とはかけ離れた別世界の住人らしいことは、朝鮮半島ウォッチャーというわけでもない私でもある程度は気づいていた。特に夫人とともに顔の整形手術を受けたという話にはぶっ飛んだよなぁ。しかし日本ではオブラートに包まれた解説とともに報道される大統領のトンデモぶりは、ごく一部であって実はまだまだたくさんあることを教えてくれるのが本書だ。
表紙はなんとも安っぽいが、著者は政治ブログ人気No.1をとったこともあるというだけに中身は実にしっかりしている。
2005年6月、日韓首脳会談のあとの記者会見の席上でノ・ムヒョンは、当時の小泉首相を横にして「夕食は軽めに作る考えです」と述べたという。つまりこれは「豪華な夕食を用意して小泉首相をもてなすつもりはない」と小泉首相本人と記者団を前にして宣言したに等しいのである。著者は「礼を失している」というより「常軌を逸している」という表現の方がふさわしいと書かれている。こうしたことが背景にあるのかどうかは知らないが、以前テレビ番組で世耕弘成参議院議員も「ノ・ムヒョン大統領は異常な大統領ですね」と淡々と語っておられた。
ほかの発言を読んでも、失笑の連続。こんな人物をよくも国のトップに選んだよなぁ、と呆れるばかりだが、支持率たった5.7パーセント(2006年12月の調査)という状態を見れば、その韓国国民からも見限られているようだ。
日本も無関係ではすまないだけに次の大統領には少しはまともな人物を選んでいただきたいものだが、誰がなるのかね。日本でもよく知られた韓国の政治家といえば国連事務総長になった潘基文(パン・ギブン)も挙げられるが、私にいわせれば外交通商相時代の発言を聞くにつけ、たいして評価はしていない。ま、次の大統領も国連事務総長も、お手並み拝見といったところか。
|
|
|
「世界の偉人たちが贈る 日本賛辞の至言33選」
波田野 毅/ごま書房/2005年 1200円 |

ご購入はこちら
|
過去に日本を訪れた外国の偉人たちは、東洋の小国に暮らす日本人が道徳心高く、礼儀正しく、しかも好奇心旺盛であることを驚き、数々の言葉で賞賛している。私も『国家の品格』に引用されていた話やアインシュタインの話など一部は知っていたが、実は歴史の教科書にも登場するような人たちが、これほどまでに賛辞を送っているということは知らなかった。
わずか20年くらい前まで、日本は世界一治安がいい国とされていたはすだ。残念ながら現在はそうではないが、これは何だかんだいっても日本人の道徳心の高さによるものではないか。あの中国の歴史書『魏志倭人伝』にも「盗みをする者も少なく、訴えごともない」と書かれているという。つまり日本人の道徳心は遠く卑弥呼の時代から連綿と受け継がれてきたということだ。
幕末、日本にやってきたペリー提督は、「実用的、機械的技術において日本人は非常に巧緻をしめしている。よって国民の発明力が自由に発揮されるようになったら、最も進んだ工業国に追いつく日はそう遠くはないであろう」とのちに書いているという。この予言はまさに的中したわけで、それを見抜いたペリー提督もすごいが、当時の技術がアメリカ人をもうならせるものであったということだろう。
読んでいくに従い、誇らしく感じると同時に、では現代の日本に生きる我々はどうなんだろうかと、恥ずかしくなった。もし過去に賞賛を受けた日本人が、今の我々を見てどう思うだろうか。偉人たちが取り上げたのは、何も位の高い人の話ばかりではない。ある人は名もなき馬子の誠実な態度に触れ、ある人は召使いがポケットに残っていた小銭に気づき盗みもせずに返しに来たことを書き残している。彼らはほかの国々と比べて、一般市民の民度が高く誠実な人が多いことに目を見張ったのだ。
戦前の軍国主義を肯定はしない。だが、過去の日本には、外国から見ても賞賛に値するものが数々あったということだ。それを全否定し、なんでもかんでも自虐的にとらえ「日本はダメなんだ」と落ち込むことはない。行きすぎた愛国心は問題だが、日本という国や日本人のよいところは自ら正当に評価し、それに自信をもち誇りをもつことは大切ではないか。
著者はいう。過去には元寇に始まり、幕末、明治初期、日露戦争、第二次世界大戦という国家的危機が何度かあった。日本はその度に巧みに乗り越えてきたが、今現在は日本人らしさ、アイデンティティーの喪失という日本史史上6番目の大危機であり、着々と進行し危機の感覚がないのが恐ろしいと。
安倍さんの掲げた「美しい国」には、そんな思いもあるのではないか。もともと日本人が元来もっていた美しいもの。それを取り戻し、未来にあっても外国の人から「日本はすばらしい」。そういわれる国に戻るため、そろそろ現代の我々自身が気づくべき時なのかもしれない。
|
|
|
「メディア・バイアス あやしい健康情報とニセ科学」
松永和紀/光文社新書/2007年 740円+税 |

ご購入はこちら
|
「発掘!あるある大事典」の一件で、テレビ番組のずさんな制作姿勢が露呈したが、このようなメディア・バイアス(情報選択のゆがみ)は、世の中にまだまだたくさん氾濫しているのを教えてくれるのが本書だ。私も以前からテレビ番組に限らず、新聞・雑誌などのマスメディアが取り上げる内容の明らかな間違いや勘違いが多いことを感じ、本サイトでも何度か触れてきたが、具体例を示して、その何がどう問題なのか、わかりやすく解説している。
あやしい科学情報が氾濫する原因として「センセーショナルな話題に引っ張られるメディアの構造、記者・取材者の不勉強や勘違い、思い込み、そして、それを利用する企業や市民団体など、さまざまな要素が絡んでいる」というのは、まったくその通りなのだが、さらにその背景には、日本の科学教育が不十分ということに加えて、もともと日本人は論理に弱いことも大いに関係しているのではないか。これはメディアが流す科学情報に限ったことではなく、いろいろな面に影を落としている。
メディアに関わる人間が、希薄な科学知識しか持ち合わせていないのは、普通にテレビや新聞を見たり読んだりしているだけで容易にわかる。テレビ番組内で行われる検証実験でも、「どうして、その結論になるの?」と疑問を感じたのは一度や二度ではない。残念ながら、これが日本のメディアの現状だ。
第9章「ウソつき科学者を見破れ」では、ロシア人科学者を俎上に上げているが、日本人科学者の中にもおかしな論理を展開している人は存在するし、知識も論理も問題なくても「落とし穴」があることもある。専門家が発する情報も鵜呑みにはできないのだ。どういうことか、本書の指摘とは別の面から、いずれ詳しく書きたいと思う。
本書を読んでいくと第2章の「黒か白かは単純すぎる」という指摘など、本サイト「世の中のウソ」でも書いてきた点と同じことが触れてあり、思わず「その通り!」と拍手したくなった。おそらくある程度の科学知識がある人なら同じことを考えていたと思うが、同意見に触れたのは本書が初めてだった。
最後の第11章「科学報道を見破る十ヶ条」は、科学報道以外の分野でもあてはまる大変重要な指摘ばかりで、もし本書を全部読む時間がなければ、ここだけでも読んでおくといい。特に「懐疑主義を貫き、多様な情報を収集して自分自身で判断する」というのは、最近、「クリティカルシンキング」とも呼ばれているようだが、そんな呼称はともかく真実を追究するには欠かせない思考法だ。でも知識だけでなく、これには想像力も重要だから口でいうほど易しくないし、大切なのは他人だけでなく自分自身の考えにも懐疑主義で望むということだから余計に難しいかもしれない。
世の中には思い込みが激しい人はいっぱいいるし、「思い込みはよくない」と頭では理解していても、実行できない人も多い。もちろん私自身も「思い込みの壺」に入り込まない保証はどこにもない。とりあえず、思い込みから離脱するきっかけにするのにも本書は役立つだろう。
|
|
|
「驕れる白人と闘うための日本近代史」
松原久子 著・田中敏 訳/文藝春秋/2005年 1524円+税 |
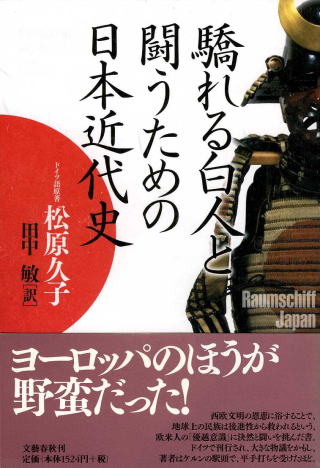
ご購入はこちら
|
タイトルを読んで感じる印象と、実際の中身は少し違うかもしれない。本書は、決して国粋主義的な内容ではない。著者は、欧米各国で講演や執筆活動をされているアメリカ在住の日本人女性である。もともと1989年にドイツ語に堪能な著者が、ドイツ語で執筆し、ミュウヘンで刊行された本が原著であり、本書は、その邦訳ということになる。「この本は、どうしても彼らに言わねば我慢できないという『激怒』と『使命感』に燃えて書き上げた」という。
訳者まえがきには、著者の松原氏がドイツのテレビ番組に出演したときのエピソードが紹介されている。それは5ヶ国の代表が討論する「過去の克服−日本とドイツ」と題された番組だった。ドイツ代表は日本軍がアジア諸国で犯した蛮行をホロコーストと同一視し、英国代表は捕虜虐待を、米国代表は生体実験や南京事件を持ち出すなどして日本を攻撃非難したという。松原氏は、ドイツのホロコーストは民族絶滅を目的としたドイツの政策であって、戦争とはまったく無関係の殺戮であり、そういう発想そのものが日本人の思惟方法の中には存在しないとし、英国代表には彼らによる日本人捕虜虐待、米国代表には百以上の日本の都市無差別爆撃を指摘したという。番組終了後、松原氏はケルン駅で番組を見た視聴者から「日本へ帰れ」と平手打ちされ、後日、このことを同テレビ番組で話したところ、お見舞いの花束がたくさん送られてきたという。その中にはこんなカードが添えられていたそうだ。「あなたのいうことは腹立たしい。でも本当だから仕方がない」。
読んでいくに従い、松原氏が相当な知識の持ち主であり、しかもその豊富な知識を背景にして、緻密で的確な分析ができる人だということに気がついた。そして、これまで何の脈絡もなく頭の中にあった段片的な知識が、ひとつにつながるのを感じた。私は、これまでも一般的な日本人の考え方の中にさまざまな矛盾やウソを感じていた。しかし、その私ですら、日本人特有の劣等感なのか、それとも戦後民主主義教育の負の成果とでもいえばいいのか、やはり強い思い込みの中にあったということを教えられた気がする。第14章の「日本人は、近代的なもの、進歩的なものはすべて欧米からくるのだというドグマに、百年以上にわたって洗脳され続けてきた」という一節、あるいは第16章の「相変わらず大部分の日本人は、自分の考えを言葉で明確かつ簡潔に表現することが苦手である。異なる意見を持っている者に対しては、冷静に言葉で防御するという能力を培っていない」という一節には、なるほど納得である。後者の指摘は中国や韓国からの非難に対してもそうだし、捕鯨問題しかりである。確かに日本人は、たとえ理不尽な意見であっても、その反論に労力を費やすことを嫌う。だが松原氏は、それに敢然と立ち向かって主張されている。外国からの批判には、なぜか無条件に萎縮する日本人は見習うべきだ。
ヨーロッパやアメリカは、世界の中枢を占め、いかにもすべてにおいて正しいかのように見えるが、彼ら自身が絶賛する欧米型の価値観にも、さまざまな問題があり、さらには彼らの歴史を俯瞰しても、決して日本が一方的に責められるほど、ご立派なものではないということ、加えていかに我々日本人は、固定観念というフィルターを通して物事(特に近代歴史観において)をとらえていたのかを教えてくれる。多くの日本人に読んでもらいたい名著である。
|
|
|
「生態リスク学入門 予防的順応的管理」
松田裕之 著/共立出版/2008年 2800円+税 |

ご購入はこちら
|
「生態とリスク」という組み合わせにピンとこない人も多いかもしれないが、人と自然が持続可能な関係を目指す上で、リスク概念は欠かせないと著者はいう。その上で、さまざまな事例を挙げながら、リスクの考え方や予防方法などについて論じている。
例えば、飲料水の健康リスク、魚の水銀含有量、化学物質の生態リスク評価、絶滅危惧植物の判定基準、風力発電と鳥衝突リスク、ヒグマの保護管理計画など。版元を見ればわかる通り、この本は一般向けの本ではなく専門書であるが、本書で扱っている内容は、自然環境問題に興味がある人にとっては関心の高い話題ばかり。難解な方程式やその説明は飛ばして、理解できる部分だけ目を通せばいい。一読をお勧めしたい。
リスクの科学は新しい学問だそうだが、それが具体的にどんなものか知らなくても論理を突き詰めて考えれば、環境問題にリスク概念が必要なのは明白であり、あとはその理論的補強が必要になってくる。それがリスクの科学というわけだ。
バス問題や犬連れ登山問題のように自然や環境に関わる問題というのは、自然という存在が身近なだけに、実は自然や生態系をあまり理解していない人も、なんだか自分もわかったような気になって、的外れな主張をされていることが多いように感じられるが、そういう方々にこそ、少しは本書のような本を読んで勉強していただきたいものだ。でも、そういう人たちというのは、もともと科学の外側にいるような人ばかりだから(だからこそ的外れな主張を平気でできる)、そんなこといっても無理だろうけどね。
|
|
|
「Lupinchen」
Binette Schroeder作/Macdonald & Co.Ltd./1970年 値段不明 |

|
子供の頃、お気に入りだった絵本は数々あったが、そのほぼすべては実家の屋根裏部屋にダンボールに入れて保管され、取りだして見ることは皆無だが、唯一、手元に大切に置いているのが、この絵本。
小学校1年生の時に世界絵本原画展が開催され、丸善の全国の支店を巡回したことがあった。それに先立ち、この絵本が何かの雑誌に紹介されていた。その絵を見て、子供心に大変惹きつけられ、丸善広島店に原画展がやってきたとき、母にせがんで連れて行ってもらった。原画を見たときのことも原画展で予約した絵本が来るのを毎日楽しみにして待ったことも今でもよく覚えている。ようやく届いたのは3ヶ月後だった。イギリスの絵本(原著はスイス)なので、本文は英語。だから父が毎日少しずつ訳してくれ、それを母が読み聞かせてくれた。
お人形のLupinchenが、なかよしの鳥と一緒に暮らすお伽の国の話だが、とにかくその絵が素晴らしい。ヨーロッパの人の美的感性は、時に非常に感心するが、こういう絵は日本人には描けないんじゃないか(国際比較すれば、日本人の感性もかなりのもんだけどね)。本文中の絵をここで紹介できないのは残念。
実はその後、岩波書店から邦訳版が出ていたようだ。それを知ったのは、2〜3年前。そこで今も販売されている岩波書店版もアマゾンで買ってみた。イギリス版のタイトルは「Lupinchen」だが、邦題は「お友だちのほしかったルピナスさん」と大きく変えられていたのにがっかり。加えて印刷の色の悪さにもがっかり。30年以上も前の方がよほど印刷がよく、これじゃこの絵本の魅力が半減すると思ったほど。
今日、本棚の片隅に封筒に入れて保管しておいた本書が目にとまったので、取り上げてみた次第。そういえば原画を見た丸善広島店は、もう何年も前に閉店し、今はもうないが、あの店の上品な雰囲気は好きだったな。高校の時は通学路にあったので、よく立ち寄っていたのも思い出す。
|
|
|
「中国はいかにチベットを侵略したか」
マイケル・ダナム 著/講談社インターナショナル/2006年 1800円+税 |

ご購入はこちら
|
著者はアメリカ人の作家で、7年もの時間を費やして、チベット抵抗運動に関わった人たちにインタビューしてまとめ上げた労作である。帯の裏面にはこうある。「これが彼らの常套手段だ!初めは友好的に振る舞い、そのうち暴力的になる。中国の侵略の実態。多くの民衆が手足を切断され、焼かれ、死んでゆく中、不気味な力に果敢に立ち向かったチベット戦士たちが伝える警告の書」。
チベット問題は、北京オリンピックの時に注目を集めたが、あのときマスコミは聖火リレーの妨害活動のような表向きの事件はしきりに報道したが、そもそもなぜチベットは中国の一地方になってしまったのか、なぜチベットの人たちは中国にこれほどまでに反発しているのか、具体的に取り上げたテレビ局は、私の記憶の範囲では一社もなかったように思う。かろうじて中国が過去にチベットに侵略した事実をごくごく地味に取り上げた番組は見たことはあるが、いづれにしろ扱いは小さかった。なぜテレビ局がチベット問題に無関心を貫いたのか。答えは簡単だ。それは北京オリンピックの前だったことに尽きるだろう。世紀の一大イベントを大々的に報道したいテレビ局としては、中国政府から目をつけられたくなかったのだ。しかも、その小さな扱いで紹介した番組では、アナウンサーが「チベットはもともと中国の一部だったのを取り戻したに過ぎない」と付け加えていたのにも驚愕した。それが事実に反することは本書を読めば一目瞭然である。1959年に国連法曹委員会は、チベットは歴史的に独立国であり、中国の一部ではないことは明らかと結論づけているという。オリンピックのためには平気で中国におもねる、このようなテレビ局に正義面してジャーナリズムだとか偉そうなことをいってもらいたくないね。
チベットに何があったのか。詳しくは本書を読まれるといい。ダライ・ラマ14世が、インドに亡命しているのは知っていても亡命に至る経緯は知らなかった。その時、ダライ・ラマは目立たないように平服を着て、国璽を握りしめてラサから脱出したという。また中共軍による、すさまじい破壊と恐ろしい所業の数々には、言葉を失うほどだ。それにしても自分たちの行為は棚に上げて何食わぬ顔をして日本の侵略行為をよくも批判できるものである。それどころか中国政府は自分たちの悪行はひたすら隠す一方で、日本の行為は全世界に吹聴してまわっているのである。そんな中国政府の本性も知らず、のんきでお人好しの、わが日本国国民は、そんな中国を非難するどころか、「大戦中に中国人民に多大な迷惑をかけました」とひたすら頭を下げて謝罪し続けているわけだ。確かに旧日本軍の残虐行為で亡くなられた中国人には、心から同情する(私は謝罪はしない。同じ日本人だから謝罪しなければならない謂われは一切ない。中国で残虐なことをした日本人と私は何の関係もない)。また過去の不幸な歴史を日本という国が二度と繰り返さないと誓うのも間違ってはいない。だが、それをあまり聲高に叫び過ぎると中国の思うつぼになるということも充分に注意しなければならない。本来は中国という国の本性を的確に見極め、彼らの戦略に載せられない賢さも必要なのだが、実際には少しも頭をかすめていないバカ正直な人が多いんだよな、日本人は。そんなことでは中国からいいように利用されるのがオチだ。
本書が指摘している全世界に対する野望がある中華思想を甘くみない方がいいというのは、その通りだと思う。尖閣諸島の問題も同じだ。つい先日の日中首脳会談でも温家宝は、日本の尖閣諸島を中国領だと主張し、すかさず麻生首相が反論したそうだが、本書を読むと似たようなことが過去にもあり、これが中国流の領土拡大のやり方だということがよくわかる。歴史的にまったく領土問題が存在しないところにも領土問題を作ってしまうというのが、彼らお得意の戦略のようだ。そして、その戦略をまんまと成功させたのがチベットなのだ。
チベット抵抗運動で戦った人たちは勇敢だ。もし、今の日本が同じ立場に立たされたら…。自己中心主義が蔓延し、自分の生活を第一にしか考えられない今の日本人に何ができるのか、自分のことも含めて考えさせられてしまった。
ところで、チベット抵抗運動に西側で唯一手をさしのべたのはアメリカだったという。CIAは、チベット人に軍事訓練を施したり、武器や資金を提供して支援したそうだ。アメリカ人作家だから、アメリカ寄りなのは当然だろうし、おそらくアメリカがしたことはチベットにとって極めて有益だったのは間違いないだろう。だが、そのアメリカも実は過去には中国と似たようなことをしている。ハワイはもともとハワイ王国という独立国だった。それが、なぜアメリカの州になったのか、知りたい人は調べてみるといい。アメリカも決して正義を貫く「いい国」ではないことがわかる。軍事侵攻していない分、中国よりかはマシという程度だろう。
|
|
|
「別冊サイエンス THE PARADOX BOX 逆説の思考」
マーチン・ガードナー 著/日本経済新聞社/1979年 1300円 |
 |
高校生の時に読んだ本なので、今はもう販売されていない。パラドックスとは、「自己矛盾を含む命題」のような意味として使われ、「逆説」とも訳される。本書は、そんなパラドックスを集めた本だが、決して難しい本ではなく、誰でも楽しく読める。例えばこんな話―。
◆プラトン「ソクラテスによる次の主張は誤りである」
ソクラテス「プラトンの主張は正しい」
◆1日に1分ずつ遅れる時計と、まったく動かない時計とでは、どちらが正確な時刻を示すか。1日に1分ずつ遅れる時計は、2年に1度しか正確な時刻を示さないが、とまっている時計は24時間の間に2回もぴたりと合う。だから、とまっている時計の方が正確だ??
中でも興味深かったのが、次の話。遠い土地などで、見知らぬ人と会って、実は共通の友人がいたりすると、驚くと思うが、この「世間は狭いね」現象に対する意外な説明。アメリカの心理学者が、次のような実験をしたという。特定の人物を出発点にして、アメリカ国内の離れた土地に住んでいる見知らぬ人物に書類を届けるということにして、最初の人は、まず目標となる人物を知っていそうな人に送り、さらにその人も別の知人に送る…ということを繰り返し、何人目で目標の人物に届くかということを検証した。検証する前、大半の人は100人くらいと予想したという。しかし、実際には書類が目標人物の手元に届くまでに仲介した人物の数は、2人から10人で、中央値は5人だったというのである。人間どうしの交友関係というのは、一本の線ではなく網目のように縦横無尽に結ばれているわけだから、意外にも緊密であることを示しているというわけ。
同じ著者のよる本は、今もいろいろ出ているので、中には近い内容の本もあるかもしれない。
|
|
|
「自衛隊秘密諜報機関〜青桐の戦士と呼ばれて〜」
阿尾博政 著/講談社/2009年 1680円 |
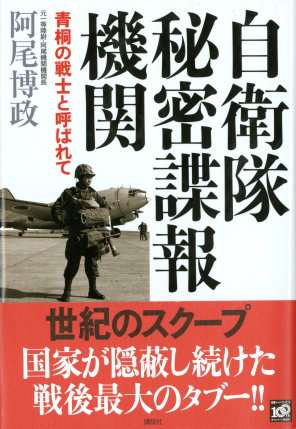
ご購入はこちら
|
自衛隊には諜報機関がないというのが建前だが、実は1965年には独自の諜報機関「阿尾機関」が作られ、諜報活動を続けていたという。本書は、その中心人物が諜報員としての半生を振り返った本で、その内容は驚きの連続だった。諜報活動というと、派手なアクションシーン満載の「007」のようなスパイ映画を思い浮かべるが、現実は、資料を集めて分析するような地味な作業も多いらしい。だが、活動をカモフラージュするために、ある時は、かつての上官にも「八百屋になりました」と偽り、またある時はスナックや洗剤販売会社を偽装経営までしていたという。徹底的にやらなければ「怪しまれる」からだそうだ。しかも、機関が誕生した時点で、表向きは自衛官を退職した形になっていたという。
本書には、李登輝、周恩来、金大中、田中角栄、笹川良一、三島由紀夫といった、著名な政治家、大物右翼、作家などが登場する。登場人物が実に多彩なのも本書の魅力ともいえるが、なによりも台湾や中国大陸での諜報活動の実態がよくわかって、大変興味深かった。
筆者は若い頃、浜口雄幸首相を銃撃した佐郷屋留雄と親交を結び、「我が師」と呼ぶ。佐郷屋は雨粒ひとつひとつが、落ちるべきところに落ちているのを見て筆者にこう語る。「人もそうだ。いろいろ考えたり、いろいろ理想を持ったりするが、やはり1点も狂わず、最後は天が定めた場所に行きつくものだよ」と。あぁ、まさにその通りだと思う。私もこの年になって、人生に「偶然」はなく、すべて「必然」のなせる技だと考えるようになった。だから、この言葉には共感できる。ここでは省略するが、そのあとに続く言葉も、深い人生経験をもつスケールの大きな人物でなければいえないものだと感じた。こういう言葉をごく当たり前に口にできる人って、今はいないなぁ。
ほかにも金大中誘拐事件や川島芳子に関する記述などもあって、内容はかなり充実している。
|
|
|
「リスクにあなたは騙される〜「恐怖」を繰る論理〜」
ダン・ガードナー 著・田淵健太 訳/早川書房/2009年 1890円 |
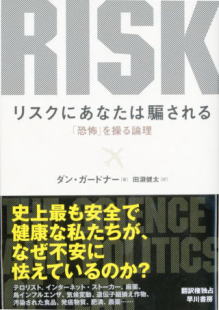
ご購入はこちら
|
私は本を読むとき、あとから再度読み直したい重要な部分があると、小さなフセンを貼り付けることを習慣にしているのだが、本書を読み終えて、いくつものフセンが付けられることになった。それほど中身の濃い本であり、目から鱗が落ちてばかりであった。
内容の特徴を説明するよりも、私がフセンを貼った部分を例として示す方がわかりやすいだろう。最初のそれは、読み始めてすぐ「プロローグ」にあった。世界貿易センタービル.へのテロ攻撃後、アメリカの人々の行動に些細な変化が生まれた。そのひとつは、移動手段として飛行機を選ばなくなったこと。あれほど強烈な映像を見せつけられては、飛行機に不安を覚えるのは当然だ。ところが、この一見当たり前に見える人々の判断が実は誤りだという。
ドイツの心理学者が、テロ攻撃前後それぞれ5年間の事故死データを比較して飛行機から車へ切り替えた直接の結果として車の衝突で死亡したアメリカ人の数を算定してみた。すると911死亡者数約3000人の半分を越える1595人という数字が出たという。実は車の衝突で死ぬ確率よりもテロによる飛行機事故死の確率の方がずっと小さく(仮に1週間に1度テロリストが飛行機を激突させたとしても)、つまり、テロという恐怖から本来はリスクがごく小さい飛行機を避けて、リスクがずっと大きい車を選んだために、おそらくそのまま飛行機に乗り続けていれば出なかったであろう死者が余計に出てしまったというのである。しかも、この事実に誰も気づいておらず、それぞれの事故死は、ありきたりの交通事故死のひとつとしか認識されていないと…。
このように具体的な例を示しながら、テロや環境を汚染する化学物質などのリスクを必要以上に恐れる人間の心の動きを認知心理学を用いて次々に説明していく。そして最終章で「今ほどよい時代はない」という結論を導き出している。帯でも評価されているように第11章「テロに脅えて」は、読み応えがあった。ただ478ページもあり、読むのは少々しんどかった。あまり意味のない形容などは省いて、もう少しスリムな構成の方がよかったかもしれない。
|
|
|
「金正日は日本人だった」 New!
佐藤守 著/講談社/2009年 1700円+税 |

ご購入はこちら
|
タイトルを見て「トンデモ本」の類かと思う人もいるだろうが、歴史観と世界観が根底から覆るほどの衝撃的な内容である。あくまで仮説だが、かなりの説得力を備えているのは間違いない。著者は航空自衛隊の司令も務めた元・空将で、取材を進めるきっかけは次のようなものだったという。ある研究会で2002年に日本海に現れた北朝鮮の不審船「金策号」について意見を述べたところ、隣に座っていた旧帝国陸軍参謀本部情報参謀の佐官だった人物から「金策(キムチェク)は帝国陸軍が半島に残した残置諜者です」と教えられる。金策とは、金日成が師と仰いでいた北朝鮮の英雄で、北朝鮮には彼の名前を付けた市や大学があり、一説には金正日の実父であるともいわれる。つまり、金策が日本人であるのなら、金正日は日本人の血を受け継いでいる可能性が生じる。
旧陸軍は、戦後、朝鮮半島にソ連が進出してきて朝鮮半島や日本が赤化する危険性まで考えて、防共のために金策=畑中理(はたなかおさむ)を金日成がいた抗日パルチザンに潜入させたという。実は金日成とされる人物は4人もいて、我々が知る金日成は、庶民から英雄視されていた金日成将軍のネームバリューを利用したニセ金日成に過ぎないといい、これはかねてより指摘されていたことだ。いずれにしろ金策はニセ金日成による政権を樹立するためにソ連に根をまわし、さまざまな助言をしてニセ金日成を支えていく。つまり、これまで我々は金日成はソ連の傀儡と思い込んでいたが、残置諜者・金策を通して実体のない「大日本帝国の亡霊」が作り出した傀儡ということになる。北朝鮮は社会主義国のように見えるが、そうではなく、むしろ日本の江戸期における封建制度に近いと著者はいう。また朝鮮戦争も金策が金日成に進言して南進させたのではないかと推測している。朝鮮戦争で一番得をしたのは、実は戦争特需で莫大な利益を得た日本であることを考えれば確かに合点がいく。
著者によれば金正日は、反日家どころか親日をも超えた「愛日家」だという。夫人のひとり高英姫は在日出身であり、わざわざ日本から料理人を招くほどの日本食好き。さらには愛車はトヨタのセンチュリーであり、執務室で使っているパソコンもNECだという。過去には極秘で訪日したこともあって、赤坂のレストランシアターで撮られた証拠写真もあるそうだ。彼は、金日成が養父であり、本当の父親は金策=日本人・畑中理であることも知っていて、日本に特別な感情を抱いているのではないかと説く。
また日本のマスコミが中国寄りの報道をする理由も述べられている。中国におもねていれば、情報収集に有利であるばかりか、現地での待遇もよくなり、記者も「特別サービス」が受けられるそうだ。「特別サービス」とは、いわゆる「ハニートラップ」である。かつて自民党の領袖クラスの大物議員が著者に語った体験談が紹介されている。初めて訪中したとき、この世のものとも思えない美しい女性が世話役として付いたという。彼女はホテルの部屋の中にまでついてきて、下着を脱ぐことまで手伝ってくれたそうだ。この議員はなんとか理性で衝動を押しとどめたそうだが、故・橋本首相がハニートラップに引っかかった(当時、週刊誌も報じた)のもよくわかる、とこの議員は語っていたそうである。
ほかにも日朝コネクションの実態、CIAと北朝鮮との関係なども語られている。我々は、北朝鮮は日本にとって最大の脅威であり、アメリカはその脅威から日本を守ってくれる力強い味方であると勝手に思い込んでいるが、もしかするとそんなに単純なことではないのかもしれない。
|
|
|

|